「鶏醤」で卵かけご飯をしてみたら「これって、もうひとつの親子丼?」って思った
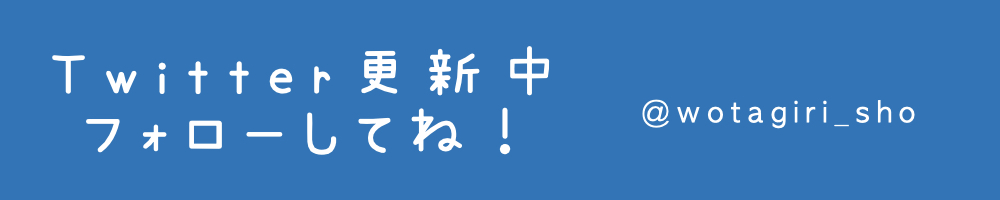
「鶏醤」って知ってますか?
今日は「けいしょう」の話をしたい。
とはいっても、誰かに何かを継承したいとか、みんなに警鐘を鳴らしたいとか、そういう難しい話ではない。先日出逢った「鶏醤」という調味料の話だ。

それがこれ。鶏油ではなくて「鶏醤」。
北海道三笠市の企業が作っている商品とのこと。

2018年の北海道・北のブランドコンテストで金賞を受賞しているらしい。
三笠市が運営する「三笠ジオパーク」のホームページにある説明を引用すると…、
三笠市内の食鳥処理場で処理された、新鮮で安全な鶏もつを主原料に、無添加かつ非加熱加工によって作られた、動物性由来「うま味」発酵風調味料です。 鶏醤には、高濃度の天然アミノ酸がたっぷり含まれており、特にうま味を引き出す成分である「グルタミン」が非常に多く含まれています。様々な料理に合う、万能調味料です。
とある。さらに調べてみると、グルタミン酸は100gあたり1,410mgで何と、
一般的な醤油や魚醤の約2~8倍
アスパラギン酸、
リジンなどの成分もたっぷり
らしい。
ちなみに買ったのは、仕事の途中で訪れた、横浜の洋光台にある「よっしーのお芋屋さん」。

焼き芋で雑誌にも登場しているお店だけど、有機野菜や全国各地の珍しい食材も売っている。
ほとんどが生産者とつながりのある商品なので、店長のよっしーさんに聞けば、食べ方や使い方を詳しく教えてくれる。鶏醤の使い方を聞いたところ「最初は卵かけご飯に使ってみては?」とのこと。
鶏醤で卵かけご飯を作ってみた
僕は人柄の良い人が言っていたことはそのまま信じる鵜呑みのウノちゃんなので、さっそく自宅で鶏醤の卵かけご飯を実践してみるのである。

まずは原料を確認。鶏モツが主原料って聞くと、クセが強いのではないかという先入観を抱かなくもない。

フタを開けてオイニー(匂い)のチェック。ん〜、醤油の匂いが薄くなった感じかな。
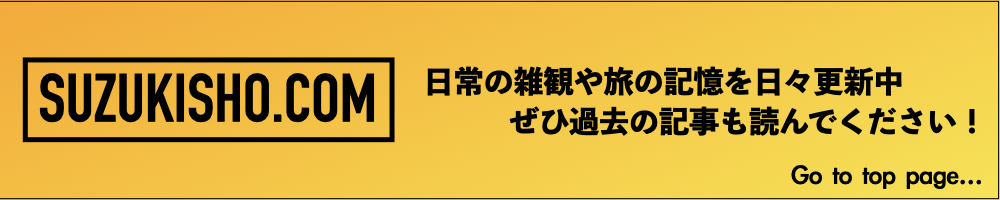
【最新ブログ-SUZUKISHO.com】
- 予定外の展開で終わり、最後にワセメシを食べた3月23日
- 有名女優の「バラエティくだらない」という放送業界への苦言は、はたして的を得ているのだろうか?
- コミケなどの大混雑イベントで東京ビッグサイトにアクセスする時はシェアサイクルの利用もおすすめ
- 渋谷のツタヤがCDとDVDのレンタルをやめるそうだ
- 【おひとりさまの鉄則】イライラを喰らいそうな人混みには他人と行くべきではない
次にお皿の上に鶏醤だけ開けてみる。これも薄口醤油に近いやや透明感のある色あい。

指につけて舐めてみると、ちょっとの量でもなかなかの塩味がある。思っていたようなクセの強さはないものの、鶏もつ特有の風味がかすかな状態で口の中にしばらく残る。
そして、こちらも買ってきたばかりの卵で卵かけご飯を用意しますた。

よっしーさんは「4滴くらい」と言っていた。
確かにこれだけ塩味が強いと、かけすぎは禁物だ。

適量をかけて、かき混ぜてみます。

見た目は普通の卵かけご飯ですわ。では、その味やいかに…。
うーむ、シンプルなご飯のために感想もシンプルにならざるを得ないのだが、何というか、普通の醤油にはない卵との一体感。それが鶏由来の調味料だからなのか、説明にある「うまみ成分」の影響ないのかはわからない。
でも、たぶん、むかし味の素のCMで卵かけご飯に味の素かけると旨いみたいのやっていたから、うま味成分の効果なんだろうなと思う次第であります。
そして、もう少し遊んでみたいと思って、冷蔵庫から取り出したのがこれ。

みざーん。これ、大人にしか分からない味ですが、山椒特有の痺れる風味がたまらんのですな。

ぱらぱらんちょーっと。(←そろそろ書くのに飽きて壊れ始めている模様、笑)
うーん、先ほどまでのバランス良い中にアクセントが加わって、これはこれでなかなか良いレボリューション。
しかしまぁ、これって鶏原料の調味料と卵のマッチングだから、ある意味でもうひとつの親子丼だな。
これは野菜炒めでちょっと味にアクセントを加えたい時にもよさそう。ほかには、ペペロンチーノなんかを作る時に隠し味にしてもいいかも。いずれにせよ、こういう未知の調味料は自炊ライフの中にいろんな想像を沸かせてくれるから面白い。
鶏醤は通販などでも買えるみたいなので、興味のある人は試しに購入してみては。

【about me…】
鈴木 翔
静岡県生まれ。東京都中央区在住。出版社や編プロに務めた後に独立。旅好きでこれまでに取材含めて40カ国以上に渡航歴あり。国際問題からサブカルまで幅広く守備範囲にしています。現在は雑誌、実用書などの紙媒体での編集・執筆だけでなく、WEBライターとしても様々な媒体に関わっています。ジャンルは、旅、交通、おでかけ、エンタメ、芸術、ビジネス、経済などノンジャンルでありオールジャンル。これまでの経験から「わかりにくいものでもわかりやすく」伝えることがモットーです。



